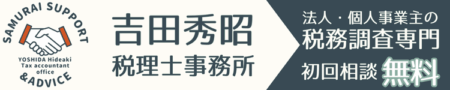Q. なぜ税務調査官は「リベート」と「在庫管理」の裏側まで知りたがるのか?卸売業の調査で見える“利益調整”のカラクリ。
A. 業種が変われば、調査官の着眼点も変わります。多くの商品を仕入れて販売する「卸売業」。この業界の調査で、調査官が特に注目するのが「リベート」と「在庫管理」という、2つのキーワードです。日々の商取引の中心にあるこの言葉から、調査官は何を読み取ろうとしているのでしょうか。
調査官は、この2つのキーワードを軸に、「利益が意図的に操作されていないか」を検証します。卸売業はモノとお金が大きく動くため、そのタイミングや評価を少し変えるだけで、利益の額を大きく変動させることが可能だからです。
例えば、こんな疑念が調査の出発点となります。 「決算期末に売上を翌期に繰り越して(売上の繰延)、意図的に利益を圧縮していないか?」 「グループ会社間で不自然な価格設定(恣意的な価格操作)を行い、利益を移転させていないか?」 「在庫の評価を不当に低くしたり、棚卸のリストから一部を抜いたりして(棚卸除外)、課税対象を減らそうとしていないか?」と。
こうした視点から、調査官は帳簿の具体的なポイントをチェックします。
- 売上: 商品が出荷されたタイミングと、売上が計上された時期は、きちんと一致しているか。
- 棚卸評価損: 在庫の評価を下げた場合、その理由(陳腐化など)に客観的で正当な根拠はあるか。
- 販売手数料: 販売促進のための手数料として処理されているが、その実態は特定の取引先を優遇する「交際費」ではないか。
「リベート」も「在庫管理」も、卸売業にとってはごく当たり前の業務です。しかし、調査官の視点を通すと、それが経営の透明性を測る重要な指標に見えてきます。日常業務の一つひとつが、会社の誠実さを映し出す鏡となる。これは、あらゆる業種の経営者に共通する、普遍的な真実と言えるでしょう。
(注)本コラムで紹介した不正計算はごく一部の事例です。大多数の事業者は、日々誠実に業務に取り組まれ、適正に納税義務を果たされています。