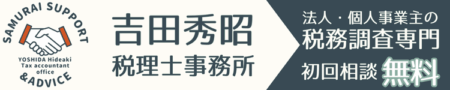Q. なぜ税務調査官は、工事の利益率だけでなく「応援する政治家」の名前まで知りたがるのか?建設業の調査で暴かれる“裏金”の流れ。
A. 業界の慣習が、税務調査の焦点を鋭くします。特に、古くからの慣習が根強く残る「建設業」。この業界の調査で、調査官が核心に迫るために尋ねる2つの質問があります。一つは「工事ごとの粗利益率」、そしてもう一つが、時に経営者をドキリとさせる「応援する政治家はいますか?」という問いです(直接は聞きませんが、探るような会話をします。)。
調査官はまず、「工事ごとの粗利益率」に注目し、業界平均や過去の実績と比較します。もし特定の工事の利益率が不自然に低い場合、「その“消えた利益”はどこへ行ったのか?」という疑問が生まれます。そして、その消えた利益が、帳簿外の資金、いわゆる“裏金”を生み出すための「架空原価」によって作り出されたのではないかと推測するのです。
では、なぜ「政治家」の話が出てくるのでしょうか。それは、捻出された“裏金”の「出口」、つまり使途を確認するための一つの切り口です。架空原価は、業界内で囁かれる談合金やバックリベート、あるいは現場の円滑な運営のための近隣対策費などに使われることがあります。そして、その使途の一つとして政治献金などが想定される場合があるため、調査官は資金の流れの“終着点”をあらゆる角度から探ろうとするのです。
この「帳簿に載らないお金や取引」という視点から、調査官は以下の点にも着目します。
- 売上: 追加工事や補修工事など、請求が漏れやすい小口工事がきちんと計上されているか。
- 工事原価: 施工の順番や支払い方法に、裏金作りを疑わせるような不自然な点はないか。
- 雑収入: 現場で不要になった中古建機や鉄くず(スクラップ)の売却代金が、申告から漏れていないか。
会社の帳簿に計上された数字と、その裏側にあるリアルな「お金の流れ」。税務調査とは、その二つが完全に一致しているかを確認する作業です。業界特有の慣習がある場合、その慣習が経営の透明性を曇らせていないか、客観的な視点で見直すことが重要と言えるでしょう。
(注)本コラムで紹介した不正計算はごく一部の事例です。大多数の事業者は、日々誠実に業務に取り組まれ、適正に納税義務を果たされています。