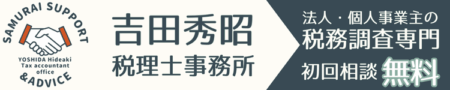Q. なぜ税務調査官は「運転日報」と「事故記録」を照合するのか?運送業の調査で浮かび上がる“帳簿に載らない稼働”。
A. 日本経済の血流とも言える「貨物運送業」。この業界の税務調査で、調査官が必ずと言っていいほど深く読み込む2つの資料があります。それは、日々の運行を記録した「運転手の乗務記録」と、万が一の事態を記録した「事故記録」です。この2つの記録を照らし合わせることで、一体何が見えてくるのでしょうか。
調査官は、これら現場の“生”の記録と、経理上の“公式”な記録を比べることで、「帳簿に載らない、もう一つの事業活動」が存在しないかを探ります。トラックが動けば、必ず売上が発生するはず。そのシンプルな原則にズレがないかを確認するのです。
例えば、乗務記録にはあるのに、売上記録にはない長距離運行が見つかれば、「“帰り便”の売上などを申告から除外(売上除外)していないか?」という疑念が生まれます。また、事故記録があるのに保険金の入金記録がなければ、「保険金収入や、事故対策のためにプールした資金(架空原価や雑収入除外)が簿外で管理されていないか?」と、お金の流れをさらに深く追っていくことになります。
この「帳簿と現場のズレ」という視点から、調査官は以下のような具体的なポイントをチェックします。
- 傭車費: 他社に仕事を依頼した記録と実態は合っているか。不自然に単価が高い(低い)取引先はないか。
- 貯蔵品: タイヤなどの消耗品について、購入記録と実際の使用・保管状況は一致しているか。(業者に預けている在庫の申告漏れなど)
- 特別償却費: 新車のトラックを、実際に使い始めた日よりも前に「事業に使った」ことにして、税金の計算を有利にしていないか。
- 雑収入: 古い車両の売却代金、新車購入時のリベート、事故の保険金、従業員からの弁償金などが、漏れなく計上されているか。
「記録」は嘘をつきません。日々の現場で生まれる一次情報(乗務記録や事故記録)と、それを集計した二次情報(会計帳簿)。この二つの情報が正確にリンクしていることこそが、経営の健全性の証です。これは、どんな業界にも通じる、極めてシンプルで重要な原則と言えるでしょう。
(注)本コラムで紹介した不正計算はごく一部の事例です。大多数の事業者は、日々誠実に業務に取り組まれ、適正に納税義務を果たされています。