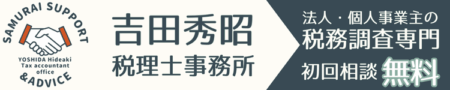Q. 「税務調査のノルマ」という“幻”。なぜ一部の国税OBは、その幻を語り継ぐのか?
A. これはあくまで私個人の推察ですが、根強く残る「ノルマ」という“幻”の背景には、国税という巨大な組織の中で働いてきた方々の、人間味あふれる3つの“思い込み”があるように感じます。
1.「目標」と「ノルマ」の混同
上部機関が組織運営の参考として示す「目標値」を、現場の職員が絶対的な「ノルマ」だと受け止めてしまうケースです。その思い込みを抱いたまま退職され、ご自身の経験として語られることで、話が広がっていったのかもしれません。
2.古き良き時代の“精神論”の名残
かつての「体育会系」とも言える職場で、先輩の「俺の時はこれだけやったぞ」という武勇伝を聞いて育った世代がいます。その中で自然と刷り込まれた「これくらいはやらなければ」という無言のプレッシャーが、退職後も記憶に残り、“ノルマ”という言葉で語られているのではないでしょうか。
3.処遇に対する“心の整理”
これは国税職員に限らず、多くのサラリーマンに共通する感覚かもしれませんが、自身のキャリアや評価に100%満足している方は少ないでしょう。その満たされない思いの原因を、自分以外の何か、例えば「厳しいノルマ」という分かりやすい言葉に求めることで、心のバランスを取っていた…という側面もあるのかもしれません。
こうした国税OBの方々の経験から生まれた「幻」が、語り継がれるうちに、いつしか世間の“常識”のようになってしまった。それが、このウワサの正体ではないかと、私は考えています。