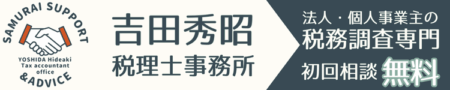Q. なぜ税務調査官は、お寺の「過去帳」や神社の「祭祀の記録」まで確認するのか? “聖域”にもたらされる“世俗”のルール。
A. まず大前提として、お寺や神社といった宗教法人の活動は、原則として法人税がかかりません。お布施や賽銭といった宗教活動そのものに課税されることはないのです。
では、なぜ税務調査が行われるのでしょうか?
それには、宗教法人が持つ“2つの顔”が関係しています。
⒈「収益事業」という“ビジネスの顔” :物品販売や駐車場・不動産の貸付など、法律で定められた「収益事業」を行っている場合、その事業から得た利益は、一般企業と同じように法人税の申告と納税が必要です。
⒉「給与の支払者」という“雇い主の顔” :事業の種類に関わらず、宗教法人が住職や神主、あるいはその家族や職員に労働の対価として金銭を支払う場合、それは「給与」とみなされます。そして、法人はその給与から所得税を天引き(源泉徴収)して国に納める義務があります。
税務調査官の目的は、この2つのルールが正しく守られているかを確認すること。そのために、彼らは「過去帳」や「祭祀の記録」いった、一見すると神聖不可侵な記録の閲覧を求めるのです。なぜなら、それこそが葬儀や行事の“実態”を証明する、最も信頼できる一次資料だからです。
この視点から、調査官は以下の点をチェックしていきます。
・葬儀収入やお布施の“中抜き”:「過去帳」の記録と、法人の収入として計上された金額は一致しているか。もし収入の一部が除外され、代表者一族の個人的な蓄財になっていれば、それは法人の収入漏れとなり個人の給与(源泉徴収漏れ)とみなされます。
・“経費の付け替え”:最も狙われやすいのが、この「収益事業」の利益操作です。本来は非課税である「宗教活動」で使う仏具、神具、衣装、あるいは代表者一族の食費といった「私的費用」を、課税対象である「駐車場事業」の経費として計上していないか。これは、収益事業の利益を意図的に圧縮する行為です。
・“幽霊職員”への給与:実際に働いていない家族を職員にしたてあげ、給与を分散させることで、代表者本人の所得税率を不当に下げようとしていないか。
・“リベート”の申告漏れ:葬儀業者や病院、墓地開発業者などから受け取る紹介料(リベート)が、法人の雑収入として正しく計上されているか。
調査官は、聖域に踏み込もうとしているわけではありません。「収益事業」と「宗教活動」、そして「法人」と「個人」。その間にある“会計上の境界線”が、ルール通りに引かれているかを確認しているのです。
(注)本コラムで紹介した不正計算はごく一部の事例です。大多数の事業者は、日々誠実に業務に取り組まれ、適正に納税義務を果たされています。