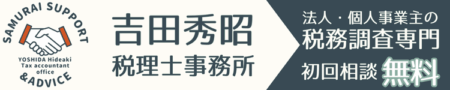Q. なぜ税務調査官は「製造現場と経理の連携」を細かく知りたがるのか?調査で浮かび上がる“構造的な問題”とは。
A. 業種によって、税務調査官が注目する「急所」は異なります。例えば、下請け構造が特徴的な機械製造業。この業界の調査で、調査官がしばしば深く掘り下げるのが、意外にも「製造現場と経理部門の連絡体制」です。この一見地味な質問から、一体何が見えてくるのでしょうか。
その背景には、元請けと下請けという、この業界特有の力関係が潜んでいます。調査官は、「現場で発生したコストや完成した製品の情報が、経理部門に正しく、タイムリーに伝わっているか」を検証することで、構造的な問題から生まれやすい利益操作の痕跡を探るのです。
例えば、現場と経理の連携が不透明だと、こんな疑念が浮かび上がります。 「元請けへの配慮から、本当は発生していないコストを計上(架空原価)し、捻出した資金で便宜を図っていないか?」 「元請けに“儲けすぎ”と思われないよう、完成した製品の在庫価値を意図的に低く評価(棚卸除外)して、利益を少なく見せていないか?」と。 情報の分断は、こうした不正の温床になり得るのです。
この「情報の流れ」という視点から、調査官は各勘定科目を精査します。
- 仕入・外注費: 架空取引の温床になりやすい、現金・単発・遠隔地の取引はないか。
- 労務費: 実際には勤務していない「幽霊従業員」への給与支払いはないか。
- 棚卸: 意図的な評価損や廃棄損はないか。外部に預けている在庫や輸送中の製品が、漏れなく計上されているか。
- 雑収入: 製造過程で出る副産物(鉄くず等)の売却代金は、きちんと収入になっているか。
「製造現場」と「経理」。この二つの部門間の風通しの良さは、健全な経営のバロメーターです。これは機械製造業に限った話ではありません。あなたの会社では、現場で起きていること、生み出された価値が、正確に経理の数字に反映されているでしょうか。その連携を確認することが、思わぬ経営リスクの発見に繋がるかもしれません。
(注)本コラムで紹介した不正計算はごく一部の事例です。大多数の事業者は、日々誠実に業務に取り組まれ、適正に納税義務を果たされています。