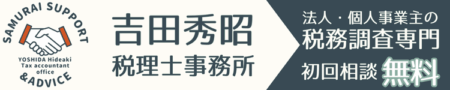Q. なぜ税務調査官は、「歩留まり」まで知りたがるのか? 調査で明らかになる“利益操作”の手口とは。
A. 税務調査官は、調査対象の業界を深く研究しています。例えば、食品加工業の調査では、彼らが必ずと言っていいほど深く掘り下げる質問があります。それは「製造工程」と、そして「歩留まり」です。一見、税金と関係なさそうなこの言葉に、一体どんな意味が隠されているのでしょうか。
「歩留まり」とは、投入した原材料に対して、どれだけの製品が完成したかを示す割合のことです。調査官がこれを知りたがるのは、業界の平均的な歩留まりと、その会社の数字を比べることで、利益操作の“歪み”を見つけ出すことができるからです。
例えば、歩留まりが業界平均より不自然に低い場合、調査官はこう考えます。 「本当は存在しない仕入を計上(架空仕入)して、原材料費を水増ししているのではないか?」 「完成した製品の一部を在庫から意図的に除外(棚卸除外)して、その分を原価に紛れ込ませているのではないか?」と。 現金取引が多く、領収書が少ない「水産加工業における浜買い」や「農産物加工業における庭先取引」などの商習慣が、こうした不正の温床となりやすいことも彼らは熟知しています。
この「歩留まり」という“ものさし”を手に、調査官は各勘定科目を鋭くチェックしていきます。
- 売上: 不自然な歩留まりを隠すため、売上単価を操作していないか。
- 売上原価: 特に現金取引や遠隔地の取引先に、架空の仕入先はないか。
- 棚卸: 在庫の単価や数量を意図的に操作したり、外部に預けている在庫を申告から除外したりしていないか。
- 雑収入: 本来は売上になるはずの魚のアラなどの「副産物」や廃棄物の売却代金が、きちんと計上されているか。
このように、調査官は業種特有の「お金の流れの急所」を熟知しています。これは食品加工業に限った話ではありません。あなたの業界の“歩留まり”は何でしょうか?その視点で自社の経理を見直してみると、新たな気づきがあるかもしれません。
(注)本コラムで紹介した不正計算はごく一部の事例です。大多数の事業者は、日々誠実に業務に取り組まれ、適正に納税義務を果たされています。